ものづくりの未来を切り拓く、エンジニアリングシステムの最前線
現代のものづくりは、IT技術との融合によって大きな変革期を迎えています。製品の設計・製造から在庫管理に至るまで、あらゆるプロセスにデジタル技術が導入され、生産性や品質の向上、効率化、コスト削減などが実現されています。これらの変革を支えているのが、エンジニアリングシステムです。
例えば、CADによる設計支援やシミュレーションによる事前検証は、開発期間の短縮と品質向上に大きく貢献しています。また、センシング技術を用いた製造現場のモニタリングや、JITやかんばん方式に代表される効率的な生産方式の採用は、在庫の最適化とコスト削減をもたらします。さらに、コンカレントエンジニアリングによって、企画・設計・製造といった各工程間の連携を強め、製品開発の迅速化と高度化を図ることも可能です。
こうしたエンジニアリングシステムへの理解を深めることは、製造業をはじめ、様々な業界で求められる人材になるための第一歩です。将来のものづくりを担うDX人材や、IT業界への転職を考えている人にとっても、エンジニアリングシステムは必須の知識と言えるでしょう。
学習ポイントをチェック
- IT技術がものづくりにもたらす変革
CADによる設計支援やシミュレーションによる事前検証など、開発の効率化と品質向上を理解する - 効率的な生産を実現する手法
JIT、かんばん方式、リーン生産方式など、在庫最適化とコスト削減につながる生産方式のポイントを掴む - 各工程の連携を強化するアプローチ
コンカレントエンジニアリングによる、製品開発の迅速化と高度化へのメリットを知る - エンジニアリングシステムを活用する狙い
FMSやMRPによる生産管理の自動化・最適化など、具体的なシステム導入の目的と効果を押さえる
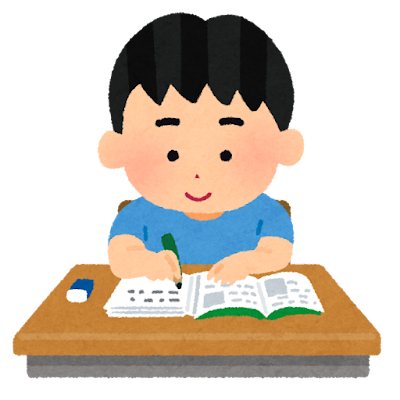
エンジニアリングシステムの基本を身につけ、ものづくりの未来を切り拓く力を養うことができるでしょう。各用語解説で理解を深めたら、練習問題に挑戦して知識を定着させていきましょう。
このページは以下の「ITパスポート シラバス6.3」学習用コンテンツです。
◆大分類:2.経営戦略
◆中分類:5.ビジネスインダストリ
| ◆小分類 | ◆見出し | ◆学習すべき用語 |
|---|---|---|
| 15.エンジニアリングシステム | (1) エンジニアリング分野における IT 活用 (2) 代表的なエンジニアリングシステム | エンジニアリング CAD(Computer Aided Design) コンカレントエンジニアリング シミュレーション センシング技術 生産方式 JIT(ジャストインタイム) FMS(フレキシブル生産システム) MRP(資材所要量計画) リーン生産方式 かんばん方式 |
エンジニアリング
エンジニアリングとは技術や工学を活用して課題を解決し新しい価値を創造するプロセスです。設計や製造、生産管理などの幅広い分野で用いられ、効率化や精度向上を目指します。
ITの活用により、シミュレーションや自動化、データ分析が可能になり、迅速な意思決定を支援する重要な役割を果たします。
エンジニアリングに関する学習用問題
エンジニアリングの特長に関して正しいものはどれですか?
エンジニアリングにおけるIT活用の例として適切でないものはどれですか?
エンジニアリングの成果として期待されるものはどれですか?
CAD(Computer Aided Design)
CAD(Computer Aided Design)は、コンピュータを利用して製品の設計や図面作成を行うシステムのことです。効率的で正確な設計が可能になり、製造業や建築分野をはじめ多くの領域で活用されています。
3Dモデリングやシミュレーションの機能を併せ持ち、開発プロセス全体の効率化に貢献します。
CADに関する学習用問題
CADの特長として適切でないものはどれですか?
CADを利用することで得られる主なメリットはどれですか?
次のうちCADが最もよく使用される分野はどれですか?
コンカレントエンジニアリング
コンカレントエンジニアリングとは製品設計と生産計画を並行して行う手法です。部門間の情報共有を密にし、開発期間の短縮や品質向上を図ります。
設計ミスやコスト増を防ぐため、設計初期段階から全工程を考慮する点が特徴です。
コンカレントエンジニアリングに関する学習用問題
コンカレントエンジニアリングの目的として最も適切なものはどれですか?
コンカレントエンジニアリングの主な利点はどれですか?
コンカレントエンジニアリングの特徴として最も適切でないものはどれですか?
シミュレーション
シミュレーションとは現実の物理現象や業務プロセスをコンピュータ上で模擬的に再現する技術です。設計や製造の効率化、リスク低減に役立ちます。
現場での試行錯誤を減らし、実験コストの削減や安全性の向上を図ることができます。
シミュレーションに関する学習用問題
シミュレーションの主な目的として適切なものはどれですか?
シミュレーションを活用することで得られる主な利点はどれですか?
シミュレーションが特に効果を発揮する場面はどれですか?
センシング技術
センシング技術とは物理的な現象や状態をセンサーを使って検知し、データとして収集する技術です。
温度や湿度、加速度、光などさまざまな情報を測定し、IoTや自動化技術、環境モニタリングなど幅広い分野で活用されています。
センシング技術に関する学習用問題
センシング技術の活用例として最も適切なものはどれですか?
センシング技術が最も関連する分野はどれですか?
次のうちセンシング技術が期待される成果はどれですか?
生産方式
生産方式とは製品やサービスを作る際の手順や方法を指します。
代表的な方式には大量生産を目指すライン生産方式、多品種少量生産に対応するセル生産方式などがあり、目的に応じて選択されます。
生産方式に関する学習用問題
大量生産に適した生産方式はどれですか?
生産方式の選択において考慮されるべき要素はどれですか?
生産方式の例として正しいものはどれですか?
JIT(ジャストインタイム)
JIT(ジャストインタイム)は必要なものを必要な時に必要な量だけ生産する生産管理手法です。
在庫の削減や無駄の排除を目的とし、トヨタ生産方式で広く知られるようになりました。
JITに関する学習用問題
JITの主な目的は何ですか?
JITを効果的に運用するために必要なものはどれですか?
JITが向いていない生産形態はどれですか?
FMS(フレキシブル生産システム)
FMS(フレキシブル生産システム)は製造プロセスの柔軟性を高めるために設計された生産システムです。複数種類の製品を効率よく生産することが可能で、需要変動や多品種少量生産への対応力が強みです。
自動化された設備や柔軟な生産ラインが特徴です。
FMSに関する学習用問題
FMSの主な特徴として正しいものはどれですか?
FMSの導入によって期待できる効果はどれですか?
FMSが最も効果を発揮する生産形態はどれですか?
MRP(資材所要量計画)
MRP(Material Requirements Planning)は生産計画に基づいて必要な資材の量やタイミングを管理するシステムです。
製品構成表や在庫情報を活用し、適切な資材調達を可能にすることで、過剰在庫や不足を防ぎます。
MRPに関する学習用問題
MRPの主な目的として正しいものはどれですか?
MRPの基本的な入力情報として正しいものはどれですか?
MRPを利用することで避けられる問題はどれですか?
リーン生産方式
リーン生産方式は、無駄を排除し効率を追求する生産管理手法です。
ジャストインタイム(JIT)の概念を取り入れ、必要なものを必要な時に生産することで、コスト削減や品質向上を目指します。
リーン生産方式に関する学習用問題
リーン生産方式の基本原則として最も適切なものはどれですか?
リーン生産方式が特に重視する要素はどれですか?
リーン生産方式における「無駄」の例として不適切なものはどれですか?
かんばん方式
かんばん方式は生産管理において必要な作業指示を「かんばん(カード)」によって行う手法です。
必要な資材や工程を明示し、在庫削減や生産の流れを最適化します。
かんばん方式に関する学習用問題
かんばん方式の目的として正しいものはどれですか?
かんばん方式の運用で必要とされるものはどれですか?
かんばん方式に向いていない生産形態はどれですか?
アンケート結果の概要はこちら
全ページ一覧



ITパスポート 試験 シラバス6.3を全面網羅した分類一覧です。体系的に全体を俯瞰しながら学習することで頭の中に知識の地図を作っていきましょう。
