社会インフラを支えるデジタル変革の最前線とは?
行政分野におけるデジタル化の進展は、私たちの生活に大きな変化をもたらしています。デジタルガバメントの推進は、行政サービスの質的向上と業務効率化という二つの大きな柱を掲げ、国や自治体のあり方を根本から変えようとしています。特に、ガバメントクラウドやベースレジストリの整備は、データ連携の基盤として重要な役割を担い、さまざまな行政手続きのオンライン化を加速させています。そして、マイナンバー制度の導入は、国民一人ひとりに番号を割り当て、行政サービスをよりスムーズに提供するための基盤となっています。
さらに、電子自治体の実現に向けて、電子申請や電子調達、電子入札といった取り組みが進められ、自治体業務のデジタル化が加速しています。また、災害時にはJアラートや緊急速報といったシステムが迅速な情報伝達を可能にし、国民の安全確保に貢献しています。こうしたデジタル技術の活用は、行政サービスの利便性向上だけでなく、透明性や効率性の向上にもつながり、より良い社会の実現に向けて大きな一歩となっています。
このような行政分野におけるデジタル化の進展にも注目していくと、今後のキャリアを考える上での視野が広がり、自身の可能性をさらに引き出すきっかけとなるでしょう。
学習ポイントをチェック
- 行政のデジタル化が求められる理由 国民へのサービス向上、業務効率化、透明性の確保など、多面的なメリットを実現するため
- データ連携基盤整備の重要性 ガバメントクラウドやベースレジストリにより、行政機関間や官民のデータ連携をスムーズにし、新たなサービス創出につなげるため
- マイナンバー制度活用のポイント 国民一人ひとりに番号を割り振り、行政手続きの簡素化や給付金の迅速な支給などを実現するため
- 電子自治体推進の取り組み 電子申請や電子調達、電子入札を導入し、自治体業務のデジタル化によって住民サービスの利便性を高めるため
- 緊急時の情報伝達の仕組み Jアラートや緊急速報で災害情報を迅速に伝え、国民の安全と安心を確保するため
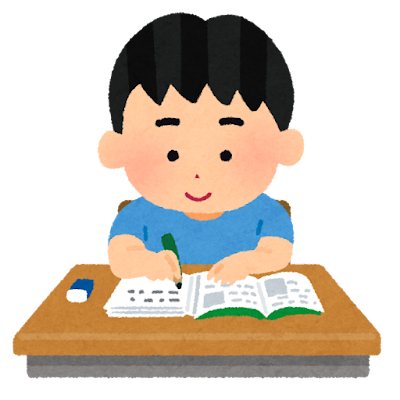
行政分野のデジタル化の最前線を理解することで、より良い社会の実現に向けた一翼を担う人材として成長できるはずです。用語解説で基礎固めをして、練習問題でさらに知識を深めていきましょう。
このページは以下の「ITパスポート シラバス6.3」学習用コンテンツです。
◆大分類:2.経営戦略
◆中分類:5.ビジネスインダストリ
| ◆小分類 | ◆見出し | ◆学習すべき用語 |
|---|---|---|
| 14.ビジネスシステム | (2) 行政分野におけるシステム | デジタルガバメント ガバメントクラウド ベースレジストリ 住民基本台帳ネットワークシステム e-Gov 電子自治体 電子申請 電子調達 電子入札 マイナンバー マイナンバーカード マイナポータル 緊急速報 J アラート(全国瞬時警報システム) |



デジタル庁のWEBサイトはシンプルに過ぎる感もありますがWEBアクセシビリティに配慮されておりますので一度目を通しておいてもいいと思います。
デジタル庁 ウェブアクセシビリティ



デジタル庁発足時にひろゆきが受けに行って落ちた(落とされた?)のは記憶に新しいですね。
デジタルガバメント
デジタルガバメントは行政手続きやサービス提供をデジタル技術で効率化・最適化する取り組みです。住民や企業がオンラインで迅速に行政サービスを利用でき、透明性や利便性が向上します。
日本ではデジタル庁が中心となり、マイナポータルや電子申請システムなどを推進しています。デジタル化によって紙ベースの手続きが減少し、行政運営のコスト削減にも寄与します。
デジタルガバメントに関する学習用問題
デジタルガバメントの主な目的として適切なものはどれですか?
デジタルガバメントの実現に向けた日本の主要な取り組みはどれですか?
デジタルガバメントの利点として正しいものはどれですか?
ガバメントクラウド
ガバメントクラウドは行政機関が利用する専用のクラウド環境で、安全性や効率性を確保しながら行政サービスを提供するための基盤です。データセンターやクラウドサービスを活用し、自治体間での情報共有やサービスの統一が可能になります。
運用コストが削減され、災害時のデータ保全や迅速な復旧も期待できます。
ガバメントクラウドに関する学習用問題
ガバメントクラウドの利点として正しいものはどれですか?
ガバメントクラウドの導入による期待される効果はどれですか?
ガバメントクラウドにおける課題として正しいものはどれですか?
ベースレジストリ
ベースレジストリとは行政が管理する基幹的なデータベースで、住民情報や法人情報などの基本的なデータを統一的に保管・共有します。複数の行政機関が同じ情報を活用でき、無駄な重複作業や手続きが削減されます。
正確で最新のデータが保証されるため、行政サービスの効率化と信頼性向上に寄与します。
ベースレジストリに関する学習用問題
ベースレジストリの主な目的として適切なものはどれですか?
ベースレジストリが活用される場面として最も適切なものはどれですか?
ベースレジストリのメリットとして適切でないものはどれですか?
住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、日本国内の住民基本台帳情報を一元的に管理・共有するシステムです。各自治体が管理する住民情報をネットワークで結びつけ、転入転出などの際の手続きが効率化されます。
また、住基カードやマイナンバー制度と連携することで、行政サービスの利便性が向上します。
住民基本台帳ネットワークシステムに関する学習用問題
住民基本台帳ネットワークシステムの主な目的として正しいものはどれですか?
住基ネットの活用例として適切でないものはどれですか?
住基ネットがもたらす行政の利点として適切なものはどれですか?
e-Gov
e-Govは日本の政府が提供する行政ポータルサイトで、電子政府サービスを包括的に提供します。申請書のオンライン提出や行政情報の検索など、国民や企業が必要な手続きを効率的に行える仕組みを整えています。
これにより行政の効率化と住民サービスの向上が図られています。
e-Govに関する学習用問題
e-Govの主な機能として正しいものはどれですか?
e-Govを利用することで期待できる効果はどれですか?
e-Govが提供するサービスとして適切でないものはどれですか?
電子自治体
電子自治体は自治体業務をデジタル化し、住民サービスの効率化や行政の透明性向上を図る取り組みです。オンラインでの住民票発行や税金支払いなど、地域住民が便利に利用できるシステムを構築します。
また、自治体間の情報連携も可能になり、災害時の迅速な対応が期待されています。
電子自治体に関する学習用問題
電子自治体の特徴として適切なものはどれですか?
電子自治体がもたらすメリットとして適切でないものはどれですか?
電子自治体で提供される可能性が高いサービスはどれですか?
電子申請
電子申請は行政手続きの申請をオンラインで行う仕組みです。申請者が窓口に出向く必要がなくなり、時間と労力を削減できます。
日本ではe-Govを通じて様々な行政手続きが電子申請に対応しており、住民や企業の利便性が向上しています。
電子申請に関する学習用問題
電子申請の利点として正しいものはどれですか?
電子申請が提供するメリットとして適切でないものはどれですか?
電子申請の導入によって可能になるものはどれですか?
電子調達
電子調達は行政や企業が物品やサービスを調達する際の手続きをオンラインで行う仕組みです。入札から契約までのプロセスが効率化され、透明性が向上します。
また、調達コストの削減や迅速な対応が可能になる点もメリットです。
電子調達に関する学習用問題
電子調達の利点として最も適切なものはどれですか?
電子調達で実現できることとして適切でないものはどれですか?
電子調達における重要な要素として正しいものはどれですか?
電子入札
電子入札は公共工事や物品調達などにおける入札手続きをオンラインで実施する仕組みです。入札の透明性や公正性が向上するとともに、手続きにかかる時間やコストが削減されます。
参加者はインターネットを通じて入札に参加でき、入札結果の確認も迅速に行えます。
電子入札に関する学習用問題
電子入札の主な特徴として正しいものはどれですか?
電子入札の導入によって期待できる効果として適切でないものはどれですか?
電子入札の利点として適切でないものはどれですか?
マイナンバー
マイナンバーは社会保障・税・災害対策における行政手続きの効率化を目的とした日本の個人識別番号制度です。住民票を有するすべての人に12桁の番号が付与され、行政機関が保有する情報を統合的に管理・活用する基盤となっています。
プライバシー保護も重視され、厳格なセキュリティ対策が取られています。
マイナンバーに関する学習用問題
マイナンバー制度の主な目的として正しいものはどれですか?
マイナンバーの利用が許可されている分野として正しいものはどれですか?
マイナンバー制度におけるセキュリティ対策として適切なものはどれですか?
マイナンバーカード
マイナンバーカードはマイナンバーを含む個人情報が記録されたICカードです。顔写真や氏名、住所が記載され、本人確認や行政手続きに利用されます。健康保険証や図書館カードとしても使用可能で、利便性が高まっています。
一方で、適切な管理と紛失時の対策が重要です。
マイナンバーカードに関する学習用問題
マイナンバーカードに記載される情報として適切なものはどれですか?
マイナンバーカードの活用例として正しいものはどれですか?
マイナンバーカードの利点として適切でないものはどれですか?
マイナポータル
マイナポータルは日本政府が提供するオンラインサービスで、個人の行政手続き情報を一元的に確認・管理できる仕組みです。利用者は自分の情報を確認したり、行政サービスの申請状況を追跡したりすることが可能です。
マイナンバーカードと連携して利用し、利便性の向上を図ります。
マイナポータルに関する学習用問題
マイナポータルの主な機能として正しいものはどれですか?
マイナポータルが提供するサービスとして適切でないものはどれですか?
マイナポータルの利用に必要なものはどれですか?
緊急速報
緊急速報は地震や津波、避難指示などの緊急情報を迅速に住民に通知する仕組みです。主にスマートフォンやテレビの緊急速報機能を利用し、瞬時に警報を送信します。
災害時の迅速な対応を支援するため、国や地方自治体が主体となって運用しています。



iPhoneでも日本の緊急速報設定ができるようになってますよね。
https://support.apple.com/ja-jp/102295
緊急速報に関する学習用問題
緊急速報の目的として正しいものはどれですか?
緊急速報で通知される内容として適切でないものはどれですか?
緊急速報の受信に必要な条件として正しいものはどれですか?
Jアラート(全国瞬時警報システム)
Jアラートは日本全国に緊急情報を瞬時に配信する警報システムです。地震や津波、弾道ミサイルの発射情報などが含まれ、防災無線やテレビ、スマートフォンを通じて配信されます。
住民に迅速かつ的確な情報を届け、適切な行動を促すことを目的としています。



JアラートもiPhoneだと緊急速報をオンにしていれば通知されますね。
https://support.apple.com/ja-jp/102295
Jアラートに関する学習用問題
Jアラートの主な目的として正しいものはどれですか?
Jアラートで配信される情報として適切でないものはどれですか?
Jアラートが配信される主な手段として正しいものはどれですか?
アンケート結果の概要はこちら
全ページ一覧



ITパスポート 試験 シラバス6.3を全面網羅した分類一覧です。体系的に全体を俯瞰しながら学習することで頭の中に知識の地図を作っていきましょう。

